「あの子、児童養護施設に入ったらしいわよ。かわいそうよね。」
先日、報道番組で流れていた再現ドラマの中でふと耳にした言葉。「施設にいる子ども」という状態を想像すれば、かわいそう、大変そうという言葉が湧いてくるのかもしれませんが、そんな連想が、施設にいる子どもたちの現在と未来を縛っているのかもしれません。
元施設職員であり、現在は児童養護施設出身者をサポートするNPOで働く伊藤翔平さんに、施設で過ごす子どもたちのこと、施設で働く職員さんのことを取材しました。

子どもはほぼ施設に溶け込めてしまうという現実
親と離ればなれに暮らすことになる児童養護施設。施設で暮らしたことがない、施設で暮らす子どもたちを知らないという側から見れば、子どもたちが施設に馴染めるのだろうかと疑問が湧きます。
「一日中泣き続ける子やしばらく一言も発さない子もいますが、多くの子どもは時間をかけずに適応します。ただ、すぐに適応できるのも良いとは限らず、適応しようとするあまり、嫌いな食べ物をお替わりしてしまったり、何にでも「はい!」と答えてしまうような「過適応」してしまう子も少なくありません。また、虐待を受けている子どもだと、親の顔色を窺ってきた時間が長いので、施設に入ると体が大きい、権力がある、口がうまいといった子どもを判断して振る舞うことができたりもします。施設に入る前に児童相談所にいる時間もありますが、そこでは集団生活になることが多いこともあって、集団で暮らすことに溶け込めてしまうと言えるかもしれませんね。」
両親の死別によって施設で生活することが多かった過去と比べ、今は虐待やネグレクト、親が働けない(病気や精神的な問題など)といった理由で施設に預けられることが多くなっています。施設に入ってきたばかりの子どもの特徴として挙げられるものはあるのでしょうか。
「施設に入ってきた子どもはまず歯医者に行くことが多いです。歯を磨く習慣がない、歯磨きしていないということがあり、虫歯だらけの子どももいます。あとは、自分の食べる量が分からない子どももいます。ネグレクトによって食事を満足に与えてもらっていないことがあり、満腹かどうかが分からず、目の前にあるものをとりあえず食べなきゃという発想に至るのです。」
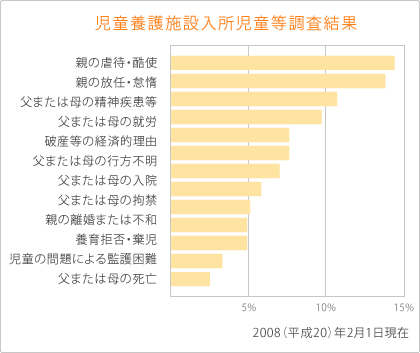
「施設で暮らし始めてしばらく経つと、施設が安心できる場所になって、だんだんと自分が出てきます。良い面も悪い面も。ただ、親の機嫌を窺ってきていたり、一般的な家族像とは程遠い環境で育ってきていたりという過去を過ごしてきているぶん、自分自身をさらけ出せることは大きな一歩なんです。さらけ出してくれると、こちらもやっと安心できるような気がします。」
施設が家となり、施設で働く職員さんが寄り添う。結果として、安心できる場所となる。支援を必要としている当事者に「居場所」をつくる運動が、様々な支援団体で行われていますが、児童養護施設は紆余曲折を過ごしてきた子どもたちにとって大切な「居場所」なのかもしれません。
施設で働く職員さんの苦労とやりがい
子どもたちの居場所をつくり、子どもの生活をサポートするプロフェッショナルである児童養護施設の職員さん。現場がタフな環境であることは想像がつきやすいものです。
「肉体的なキツさもあるのですが、自分が育ってきた価値観や倫理観、環境が試されるというほうが厳しいかもしれません。目の前で死にたいと言われたり、リストカットされたりというときに、自分がどう対処していくのか人間力が試されます。新卒だとほぼ最初は対応できないですもんね。嘘はバレたら最後ですし。僕もだいぶ鍛えられました。」
少しずつ子どもとの関係構築ができたり、成長を見届けたりしていくとやりがいが増していきます。実際にはどんな場面でやりがいが生まれるのでしょうか。
「子どもを相手にしているので、常に日々何らかの成長が感じられるんです。僕の場合は小さな成長のほうが嬉しくて、トマト嫌いだった子が5年かけて食べられるようになったとか、相手のことを気にかけられなかった子が気配りできるようになったとか、そんなひとつひとつが嬉しい。あと、子どもっていたずらしたり、子ども同士でけんかしたり、いつも何か起こるんですよ。自分が凹んでいてもそんなヒマを与えてくれない。いい意味ですぐに切り替えていける。やりがいはすべて子どもに集約されますね。」

施設で暮らす子どもたちと親との関係性
全国に600ヶ所近くある児童養護施設。両親不在という理由で施設での生活が始まる子どもが少ない現在、施設で暮らす子どもと親との関係性はどのようなものになっているのでしょうか。
「お父さんが子どもをつい殴ってしまい、お母さんがそれを抑えられない。そこで子どもが大きくなるまで待ちましょうとか、1回時間を取りましょうとか、児童相談所から提案して、お母さんから了解を得る。これは子どもが施設に行くまでの流れの一例ですが、ほとんどの場合、親の了解を得た上で、子どもは施設での生活が始まるんです。したがって、親のどちらとも面会できないという子どもは多くありません。「住んでいる場所が施設」というイメージのほうが近いのかもしれませんね。中学校卒業とともに家に帰るとかもありますし、施設にいる期間もまちまちだったりするんですよ。」
児童養護施設は親と子の間にうまく入って、子どもの生活をサポートしているという認識のほうが、実状に合っているようです。
「児童相談所の福祉司さんが施設を選定するのですが、施設にも低年齢児を受け入れている、中高生が得意といった特徴や強みがあるんです。必ずしも該当する施設に入れるわけではありませんが。相談所と親御さんとの間にも関わりはあるので、施設と相談所と親御さんと三者が連携して、できる限り子どもの現状に合った場所で育てていると言えるのかもしれません。」
児童養護施設のこれから
10年前からボランティアとして関わり始め、6年前から職員として勤めていた児童養護施設を辞めた伊藤さんは今、施設出身の子どもたちを広くサポートするNPOで働いています。施設の内部を知り、今では施設出身者と社会の接点を作る活動をしているからこそ感じていることを最後に聞きました。
「施設にいる子どもたちの環境をもっといいものにしていくためには?と考えたとき、個人的に行き着いた答えが児童養護施設の職員という仕事の社会的認知を高めることでした。憧れられる職業にして、どんどん有望な人材が職員として増えればいいなと思います。一般常識を知らない施設職員がいれば、子どもたちの常識観に影響を与えてしまいます。離職率が高ければ、子どもが職員との信頼関係を毎回毎回作らなくてはいけなくなり、ストレスを抱えてしまう。大人を信用できなくなってしまうことにもつながりかねません。社会的認知が高まれば、給料も上がり、ひとも集まりやすくなり、やりがいも上がる。結果的に子どもの環境が改善されていくと思うんです。これは施設の中で働いているとなかなかできないことなので、新たな環境に身を置きました。」
若手世代は兄や姉のように、中堅世代は親のように、ベテラン世代は祖父母のように。拡大家族のようなコミュニティとして子どもたちを育てていくのが児童養護施設です。人間力があったり、想いが強かったりと、何をもって有望な人材と語るかは難しいですが、少なくとも「児童養護施設の職員」という仕事の魅力が広がらなければ、集まりづらいのは事実でしょう。
「児童養護施設そのものも里親制度との兼ね合いもあり、役割が変わっていく節目が来ています。大きい視点で言えば、社会的養護の中で児童養護施設がどうあるべきかを考えなくてはいけませんし、小さい視点で言えば、職員一人ひとりが子どものために何をすべきか、施設としてどうあるべきかを考えなくてはいけません。私自身、児童養護施設は地域の子育て支援の拠点になるべきところだと思っていますが、その持論を展開していくために、施設から移ってきたので、やるべきことが山積みです。」

元々、子育ては家族だけでなく地域ぐるみで行っていくことが多かった日本。社会で子どもを育てるという社会的養護の考え方から見れば、実は児童養護施設がその中心に立ち、地域と連携しながら子育てを担っていけるのかもしれません。両親ともに風邪を引いたから短期間施設に預ける、育児の相談先として施設を利用するといった場面も、突飛なアイデアですが、ひとつの理想像としてあり得ることだと思います。
児童養護施設は子どもの生活をサポートするプロフェッショナルである。社会全体がそんな認識を得ることによって、今、施設で暮らしている子どもたちに降りかかるイメージを取り除くことができるとともに、前途有望な若者がこの仕事を志望したり、人生経験豊富なベテランが現場に関わり始めたりするようになるのかもしれません。
児童養護施設が、タフな環境を乗り越えてきた子どもたちにとっての「居場所」だけでなく、子育てに関わるすべてのひとにとっての「居場所」となるのであれば、日本の未来を担う子どもたちにとって非常にポジティブなものになるのではないかと思います。