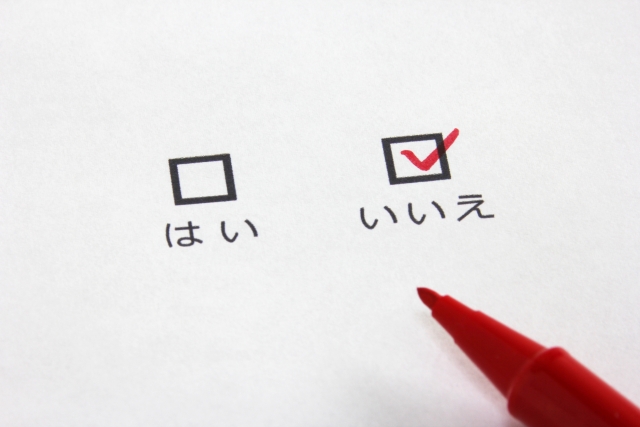-
 business
business
聞こえづらさへの配慮は、障害への配慮というより職場の環境改善への一歩ではないか?
「耳が遠い」という自覚は小学生の頃からありました。昔も今も健康診断の聴力検査では左右ともに「所見あり」。後天的な原因ではなく、遺伝などの先天的なものだという診断を受け、「聴こえ」と同じく「聴き分け」が難しいのだろうと言われました。聞こえづらさを抱えていると、仕事上のコミュニケーションでいくつかの問題が発生します。 -
 business
business
新入社員に告ぐ!君たちは無価値だ!!
4月1日。期待と不安が入り混じりながら社会人のスタートを切ったばかりの新入社員のみなさんはたくさんいると思います。私も新入社員の頃はそうでした。もともと自信過剰気味の私は、あまり口には出さずとも「バリバリ働いて、出世してやるぜ!」という気持ちを抱いていました。そんな気持ちは入社3ヶ月目、座学中心の研修期間が終わり、部署に仮配属という形で配属されてすぐにぶち壊されます。 -
 business
business
新卒の教育なんかしない!自称ブラック企業が教育を放棄した新しい採用方法をスタート
世の中の経営者はみんな、本音と建前を使い分けながら経営をしているものだと思っていました。株式会社セブンコードの代表である濱野氏に会うまでは。 濱野氏と知り合うきっかけは、ニュースアプリで見つけた「『他社で新 […] -
 business
business
えっ!訴えられる!?2016年4月からの「障害者差別禁止指針」「合理的配慮」の注意点
2016年4月より「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮」を企業は実施しなくてはいけないことになりました。障害者差別解消法の施行によるものです。今回は、それに伴う障害者側と企業側における注意点を書いてみます。障害者差別禁止指針では、すべての企業を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めています。 -
 business
business
内定ブルーはこうして吹っ飛ばせ。5つの心得。
リクルートスーツを目にすることが多い季節になりました。就活が終わった人の中には「自分にもこんな時期があったなぁ」と、たった一年前のことなのに懐かしんでいる人もいるかもしれません。せっかく就活が終わっても、それだけで安心ができず自分の内定先について「企業名 ブラック」なんてキーワードで毎日検索している人もいることでしょう。 -
 business
business
うつ病から社会復帰への道のりー復職の難しさと心の波を乗り越える
うつ病になって退職して、また働いてみようともがいていたとき。平日は異常に緊張していて、週末になるとその糸が切れて、心の底からホッとしていました。そんな毎日を経て、ようやく人並みには働けるようになったかなと思う今。あのときの気持ちの波を思うと改めて、復職は難しいことだと思います。 -
 business
business
3年で辞める若者のホンネーネガティブ早期離職者のリアルー
新卒入社後3年以内で3割が退職するという「3年3割問題」は若者叩きの格好の材料として使われるネタですが、実はこの状況は20年前から変わっておらず、今の40代の方も若者のことは笑えません。そもそも3年で3割辞めるのは悪いことなのかという点についても、様々な意見があります。私は3年以内で辞めた100名以上にインタビューをしましたが、退職には「ネガティブな退職」と「ポジティブな退職」があることが分かりました。 -
 business
business
ストレスチェック義務化でますます生きづらい世の中になる?
2015年12月1日から企業が従業員に対してストレスチェックを実施することが義務化されました。そんなストレスチェックの実施に伴って、こんな意見が出ています。「『めんどくさい人』の魔女狩りになるのではないか?」「メンタル面で弱い人のあぶり出しや、追い出しに使われるのではないか?」ストレスチェックの結果を理由に休職や退職に追い込むのではないか。または、評価や昇進の材料に使うのではないか。そんな心配です。 -
 business
business
スポーツに便乗した流行りのマネジメント論には気を付けろ
「ビジネスでは野球と政治と宗教の話はご法度」という言葉があるそうですが、会社の組織運営やマネジメントに関して、野球やサッカーなどのスポーツを引き合いに出して説明する人は少なくありません。 最近では歴史的大番 […] -
 business
business
部署異動が原因でうつ病になった僕が思う、異動直後にしておきたい(してほしい)職場の同僚とのやりとり
「うつ病ビギナー(初心者)に贈る言葉」というコラムを以前書かせて頂きました宮原と申します。 僕は、大学を卒業して、新卒で一般企業に入社しました。そして、2009年7月頃〜2011年1月頃のおよそ1年半の期間 […]